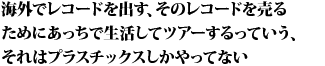

★プラスチックスは80年にメジャーデビューしてますけど、当時メジャーデビューするのってかなり大変なことでしたよね?
「そうだね。だからもうロックというよりは、歌謡曲の扱い? ちょっと普通のレコード会社から出そうとすると、『夜のヒットスタジオ』(※テレビ音楽番組)に出るとか出ないとか、すぐそういう話になるから」★(笑)。
「やっぱり芸能色が強かったかなあ。じゃなかったらものすごいマイナーとかアングラでやるか。新宿とか下北とか高円寺とかのすごい小っちゃなライヴハウスでやり続けるか。もっと中間があってもいいんだけどね。まあ、いまでは笑い話みたいな時代(笑)」★(笑)でもこの頃プラスチックスは、かなり海外でも活動してましたよね?
「うん………外国の方が活動のメインになっちゃったよね。あっちでレコードを出す、そのレコードを売るためにあっちで生活してツアーするっていう、それはプラスチックスしかやってない」★そうですよね。
「別に日本はどうでもいいやってつもりは一切なかったんだけども、ただ当時は日本とあっちとの落差がすごいあったからね」★はい。
「日本だとコンサートっていうと、客席があって、バンドが出てくるとみんな拍手して、一曲目が始まってちょっと身体揺らして、で、ノッてきて立って踊りたいんだけど、周りを見ると、みんな立ってないから………どうしようかなあみたいな(笑)」★ははははは。ありましたねえ、そんな感じ。
「いや、それがフツーの時代だから。それに対して(ニューヨークでプラスチックスがライヴ出演もした)マッドクラブとかハラーとか客席なんかないから。スタンディングのクラブだから。ステージに出たらみんな勝手にノッてて。そこの差は大きい」★じゃあ、そのギャップを引き受けながら日本と海外を往復する活動って、かなり大変だったんじゃないですか?
「うん、ノリが悪いって意味じゃないんだけど、逆に日本はよっぽど盛り上がらないと自然に立ち上がってくれないからね。それが出来なかったプラスチックスはダメってことなんだけども。だから海外の方がやりやすかったのかも」★これは(中西)トシさんとも話したんですけど、プラスチックスって81年で解散するまでの2年間で、ものすごい活動量ですよね?
「うん。丸2年やって、3枚(のアルバムを)出して、ずっとアメリカ/ヨーロッパ・ツアー回って---------まあ、若かったから出来たっていうか、怖いもの知らずっていうか」★そんな活躍をしてるにもかかわらず、81年にプラスチックスは解散してしまうんですけど、これはどうしてなんですか?
「プラスチックスは、日本にもあたらしい伝統とあたらしい意識をもった若いのが居るんだっていうのを(世界に)見せつけてやろうっていうのもあって(海外へ)出てったわけなんだけれども---------ただ、日本人がギターとかシンセでやってるだけで、もうなんかミステリアス? 着物とか琴とか三味線使わなくても、日本人がリズムボックスでロックをやってるっていうだけで、かなりエキゾチック? だからそういう意識をもった若いのがいるっていうアピールは充分出来たと思うんだけど、やっぱ、次はその上のレベルにぶち当たっちゃうわけだよね」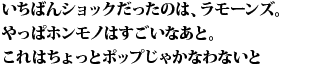
★とういうと?
「もうその上のレベル(の評価軸)ってボーダーレスで、ただ『いいものはいい』っていう。もうエキゾチックとか、日本人がロックとか、そんなの関係なくて。そうなるとやっぱり上には上が居るっていうか。その代表がラモーンズで」★ふーん。
「ラモーンズとはバークレーの郊外(のコンサート)で、対バンでやったことがあって---------前座じゃなくって対バン。プラスチックス“と”ラモーンズ。前座じゃないから!対バン、対バン!相手にとって不足無し!やったろうじゃん!みたいな。……そしたら全然かなわないっていう」★ははははは。
「かなわないどころか、もう口あんぐり。プラスチックスもそれなりに受けてみんな『イェー!』って感じでノッてるんだけど、ラモーンズが出て行くともう(会場ごと)ドッカ〜〜ン!!っていうか、地鳴りがするっていうか」★へえー。
「(ラモーンズって)楽屋ではみんな暗いんだよね。外国のバンドってバカっぽい盛り上がりが多いんだけど、ラモーンズは楽屋に挨拶に行ったらみんな(孤独そうに)頭かかえて(自分の世界に入っちゃって)るみたいな」★(笑)。
「挨拶してもほとんど一言『………ハイ』くらいで、握手もなし。この人たち大丈夫かなあ、やる気あんのかなあみたいな(笑)。………でもすごいよ、本番になると」★あ、ステージでは変わっちゃうんですね?
「すっごい。ああいうところすごいね。表現者だね。なんかものすごいアーティストっぽいっていうか、なんか本当のミュージシャンシップみたいなものを初めて見たような気がした」★へえー。
「やっぱホンモノはすごいなあと。これはちょっとポップじゃかなわないと。それで僕はポップとかロックっていうのは、ちょっともういいやってなって、中西(トシ)・(佐藤)チカはもっとポップやロックをやっていきたいってなって、ニューヨークでメンバー集めてMELONを始めて---------」★へえー、そういう経緯だったんですか。じゃあ、プラスチックス解散の引き金となったのは、対バンのラモーンズだったという?
「いちばんショックだったのは、ラモーンズ」★まあ、ラモーンズはやっぱり、すごいですよね(笑)。
「……うん、比べる方が悪いっていう(笑)。ラモーンズなんか相手にしてたら命がいくつあっても足んないよって(笑)」★ははははは。
「でも、いまになって思えば、あまりにホンモノはすごい、プラスチックスはあまりにもインチキであまりにもニセモノだ。でもそこがいいんじゃん!っていうふうに考えればよかったんだけど、そのときはそういうふうに考えられなかったから」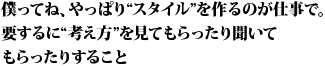

★そこから今度は音楽性も変わり、ソロ・アルバムの方へ活動がシフトしていくわけですけど。
「グラフィックの仕事に戻ってもよかったんだけど、たまたまサキソフォーン・カルテットっていうか、ジャズでもないしクラシックでもないし前衛でもない、ちょっとやってみたい音楽があったから、それを試しにやったら形になったんで、『H』、『Hm』と(ソロ・)アルバムを2枚作って」★素晴らしいアルバムですよね。
「でも僕ってね、やっぱり“スタイル”を作るのが仕事で。要するに“考え方”とかを見てもらったり聞いてもらったりすることが多いから、あんまりパート2とかパート3ってやりにくいんだよね。『H』でも『Hm』でも、ああいうノンカテゴリーの音楽って、考え方とかスタイルは僕が提案したと思うけども、その後はもっと本当にサックスが上手い人が展開していった方が、より一般的にはわかりやすいものになったりするよね」★なるほどね。でもそのスタイルの提案ってことでは、ある意味プラスチックスもそういうものなんですか?
「プラスチックスもまったく一緒。そういう考え方を見てもらったり聴いてもらったりしてるって意味では、まったく一緒。たとえばグラフィックの仕事の中でも、<タイポグラフィー>ってシリーズがあって、あれは『いまタイポグラフィーって何なのか?』っていう考え方を見てもらってるわけだから」★なるほど。
「僕があそこでタイポグラフィーをやるまでは、タイポグラフィーなんてデザイン界でも死語になりつつあって、レタリングなんてまさに流行らない作業? だっていい書体/フォントがいっぱいあるのに、なんで自分でダサイ字を作らなきゃいけないの?って。そこで、いまタイポグラフィーって何なのかって考え方をプレゼンしているわけ」★はい。
「それはプラスチックスの時もそうだし、『H』『Hm』のときもそうだし。個展やってても、音楽やってても、グラフィックやってても、<アプリケーション>やっててもそこは変わんない」★うん。
「今回のTHE CHILL(※7月4日にアルバムもリリースする立花ハジメ率いる人力ハードエレクトロサイケバンド。G.立花ハジメ、Vo.紺野千春、Dr.屋敷豪太、B.杉本邦人)もまったく一緒だよ。プロモーションビデオもあるし、バンドっていう実体もあるけど、なんでいまCHILLなのか、CHILLって何なのかっていう」★久々のバンドですよね。
「THE CHILLはとにかくツアーをやりたい。ライヴがいいバンドだからとにかくライヴをいっぱいやりたい。話があればどこでも。今回僕がTHE CHILLでやろうとしてるのは、“旅”じゃなくて“移動”。<移動距離>と<移動回数>。移動しながら物作り。<移動距離>と<移動回数>と<アイデア>は正比例するっていうふうに僕は思ってて、今は」★へえー。
「旅をしながら物作りをする人はいるし、みんなもできればそういう生活がしたいと思う。でもなかなかお金と時間が許してくれない。じゃあさらにそれを進化ってわけじゃないけども、旅じゃなくてもいい、とにかく<移動距離>と<移動回数>を稼ぐ。とにかく留まってちゃダメ。それをやればやるほどいい曲が書ける、いいデザインができる。それを今年はやってみようと。だからいまはそれに向けてかなり打ち込んでやってますね」■80’s お宝紹介
 当時、ニューヨークのカナルストリートにあるプラスチック屋さんで見つけたプラスチックの素材ですね。東京で言うと浅草橋(の卸問屋街)みたいなところ。
当時、ニューヨークのカナルストリートにあるプラスチック屋さんで見つけたプラスチックの素材ですね。東京で言うと浅草橋(の卸問屋街)みたいなところ。
形は何でもあるんだけど、僕は平ぺったい丸と、このキューブのシリーズを集めてて。お店自体が現代美術の作品みたいなところで、だってこれが陳列棚にどわっとあって、それをジェリー屋さんとかお菓子屋さんのように、気に入ったのをトレーにどんどん取っていくんだから、それだけですごいじゃん?お店だけでスーパーキッチュだよね。
しかもこのキューブ、角が丸まってるでしょ?これちゃんと面取りしてあるんだよね。これだけでもう作品っていう。
でもこのお店、いまもまだあるかなあ?
インタビュー:井村純平(TOKIO DROME/WISDOM)
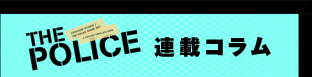
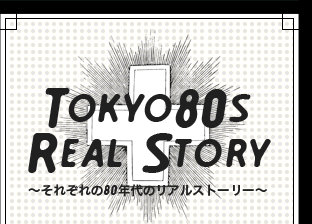
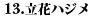

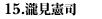


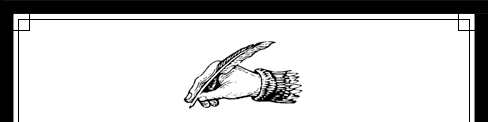
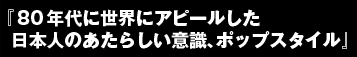
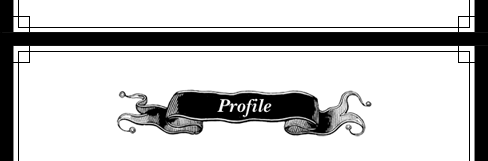
 1973 早稲田大学在学中、1年間ロンドンに滞在、カムデン・アート・センターにて学ぶ。
1973 早稲田大学在学中、1年間ロンドンに滞在、カムデン・アート・センターにて学ぶ。
 5.29(tue)LIQUIDROOM
5.29(tue)LIQUIDROOM